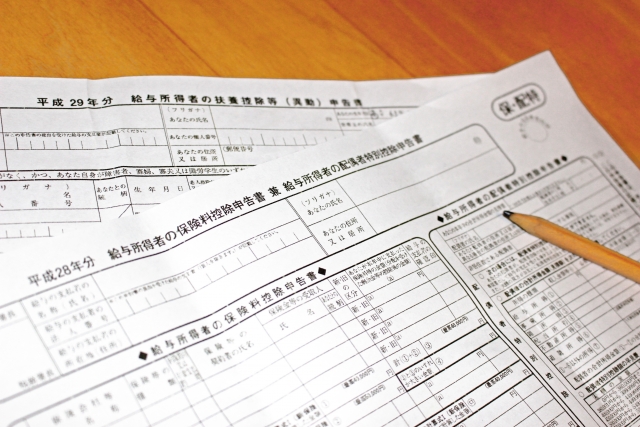
サラリーマンの場合年末において最後にもらえるお金として年末調整があります。
しかし。。。この年末調整って必ずしももらえるものではありません。
マイナス表示になっていてさらに引かれていることもあります。
どうして。。。マイナスになるのだろう?
マイナスになるには何らかの理由があるのでしょうが、その原因とは?
目次
◆税金の源泉徴収の仕組みについて
年末調整がマイナスになる理由は、いろいろあります。
そのことについては税金の源泉徴収の仕組みを理解すると分かりやすくなります。
ビジネスパーソン(会社員、事務員)の場合、給料が毎月支払われます。
その際においてですが、源泉所得税は天引きとなっています。
このときの税金の計算は、二つの要素で決まってきます。
一つがその月の社会保険料等控除後の給与等の金額で、
もう一つが扶養家族の数になります。
・社会保険料控除後の毎月の給料
・扶養親族の数
この二つの要素で、
税額表に示された金額が税金ということで毎月徴収されています。
源泉徴収税額表(給与所得の源泉徴収税額表(月額表))>>>
・賞与(ボーナス)の場合
もう一つの収入である賞与(ボーナス)の場合も、
二つの要素である社会保険料と扶養家族数ということは変わりないのです。
ですが、賞与の場合においては、
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額ということになっています。
そして、これらの要素に基づいて算出率が決まります。
どういうことか分かりやすく言うと、
賞与の場合は時間外手当などで前月の給料が多いと税率が高くなります。
その結果、賞与でたくさんの税金を徴収されます。
逆に前月の給料が少ない場合ですと、
税金は少なく徴収されるということになります。
ですから賞与(ボーナス)の場合も結局は、
・社会保険料控除後の毎月の給料
・扶養親族の数
が算出要素となります。
源泉徴収税額表(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)>>>
・年末調整における控除
税の仕組みとして、給与と賞与の占める割合をある程度予測して、
徴収する税率や税額を決めているのです。
そのため給与と賞与が全体収入に占める割合で予測と変わるという結果になります。
そして、年末調整の際には生命保険料控除や地震保険料控除などがあります。
これらの控除は毎月の天引きには反映されていません。
ですので、それらの申告をすると、
その分に相当する控除分は給与と賞与の占める割合の予測の範囲外となります。
ですから、基本的には多めの税額が徴収されています。
その結果、年末に再計算されて税金の返還ということに結びつきます。
大方の仕組みは以上のとおりです。
◆マイナスになる原因とは?
ある程度はですが源泉徴収税額表により、
年末調整においてプラスやマイナスが出ないようになっています。
とはいうものの人によって様々なことがあります。
それらに関係するもので、具体的な還付や追加徴収が決まってきます。
・一番多い理由としては扶養家族の減少
マイナスになる理由としては扶養家族の減少があります。
年末調整においては書類書く際において扶養控除等(異動)申告書があります。
この時に例えば奥さんや子供が扶養を抜けていた場合は
控除される金額が減ります。
その結果調整として再計算されてマイナスとなるのです。
・賞与の額が多かった場合
賞与の額が毎月の給料に比べて割合的に多い場合は、
年収が増えているのに毎月の給与からの徴収税額が少なくなります。
これは賞与(ボーナス)においても、
・社会保険料控除後の毎月の給料
・扶養親族の数
が算出要素となるからです。
つまり賞与(ボーナス)の税率は、
賞与(ボーナス)を受け取る月の前月の給料の金額で算出されます。
給料はいつもと変わらないがボーナスの割合が増えた場合、
ボーナスにかかる所得税は本来かかるべき税額より少なく徴収されています。
ですので、年末調整でマイナスになります。
さらに、賞与支給の前の月の給与額が少ない場合も賞与にかかる税率は低くなります。
その結果として徴収税額が収入に見合っていないことから、
年末調整ではマイナスになるという具合です。









