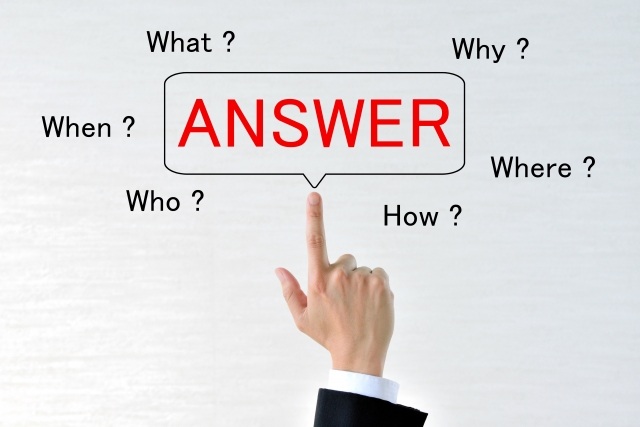
独壇場(どくだんじょう)と独擅場(どくせんじょう)は、
どちらも同じような読み方で、同じような字を書きます。
ですが「つちへん」と「てへん」で、
読み方が「だん」と「せん」となり異なります。
これらの文字が似ていて混同されることが多くあります。
独壇場(どくだんじょう) 独擅場(どくせんじょう)の違いとは?
目次
◆独壇場(どくだんじょう) 独擅場(どくせんじょう)の違い
結論からいえば、独壇場(どくだんじょう)独擅場(どくせんじょう)の違いは、
文字の表記と読み方が異なるだけです。
つまり、意味は全く同じと考えられます。
しかし、元々は独擅場(どくせんじょう)が正解とされ、
独壇場(どくだんじょう)は誤用から生まれた言葉となっています。
◆「独壇(どくだん)」という言葉は存在しない?
独擅場(どくせんじょう)は「独」と「擅」と「場」で成り立っています。
「独」とは「ただひとり」という意味です。
「擅」とは「独り占めにする」「かって気ままにする」とされます。
ですから「独擅(どくせん)」の意味は、
「自分ひとりが思うままに振る舞うこと」となります。
そこに場の一文字が付いて独擅場の言葉が成り立っています。
一方、誤った読み方から生まれたの独壇場(どくだんじょう)ですが、
まず「独壇」という言葉自体がそもそも存在しません。
ですから、明らかに間違っていることが分かります。
なぜ独擅場(どくせんじょう)は独壇場(どくだんじょう)と誤ったのか?
◆どうして誤って読まれるようになったのか?
「独壇」という言葉はありません。
しかし「壇」という言葉自体はあります。
例えば「仏壇」とか「教壇」です。
これらに使用される「壇」の意味は、
「土を盛り上げてつくった儀式を行う場所」「他より一段高くこしらえた場所」
となります。
けっこう一般的に日常で使用される頻度も高いです。
それに加えて、「擅」と「壇」の文字は非常によく似ています。
「どくだんじょう」と誤って読まれるようになりました。
また、独擅場(どくせんじょう)の意味は、
特定のひとりだけが思いのままの振る舞いができる場面や状況のことです。
「独断」という言葉があります。
「独断」とは「自分一人の考えだけで物事を決めること」です。
この場合「段」の字が違いますが意味的には似ているところがあります。
ですから独擅場(どくせんじょう)を、
独壇場(どくだんじょう)と読み間違えても違和感がなかったかもしれません。
◆最後に
現状においては独擅場(どくせんじょう)が正しく、
独壇場(どくだんじょう)は誤用という位置付けになっています。
辞書においても「擅」を「壇」と書き誤って生じた語となっています。
ただし、独壇場(どくだんじょう)の使用は一般化されています。
ですから、両者はどちらを使用してもOKとなり得るでしょう。









