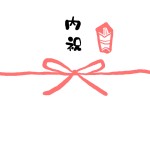正月にしか食べられない料理といえば『おせち料理』があります。
いろいろな食材が入っているおせち料理は見ているだけで楽しいものがあります。
そんなおせち料理に使われている食材には、
いろいろな新年への願いや意味が込められています。
何も食べずにおせち料理を食べるのではなく、
意味や由来を考えながら食べるとより美味しくなりますよ。
目次
◆おせち料理に使われる食材の意味
おせち料理にはいろいろな食材が使われ、正月の風景を楽しませてくれます。
そんなおせち料理に使われている食材には、それぞれの意味が込められています。
例えば。。。
おせち料理の定番の「エビ」には、
長生きするようにと長寿の意味が込められています。
これはエビの腰が曲がっていることから、
食べた人もエビと同じように腰が曲がるくらい生きてほしい。
そんな願いが込められているのです。
ほかにも。。。
カズノコは『子孫繁栄』
黒豆は『マメに働けるように』
紅白かまぼこや紅白なますのように、紅白はおめでたい事の象徴でもあります。
伊達巻は『昔は大事な文書や絵は巻物にしていたので学業成就』
栗きんとんは『黄金色に輝く財宝』
昆布巻の昆布は『「喜ぶ」の言葉にかけ健康長寿』
ごぼうは『細く長く幸せに』
するめは『「寿留女」と書くことで祝い事を表す縁起もの』
などいろいろな願いが込められています。
このように
おせち料理に使われている食材には1つ1つに由来や願いが込められているのです。
◆おせちを入れる重箱にもある新年の意味
食材にも込められているおせち料理の意味ですが、
おせち料理に使われる重箱にも意味が込められています。
『おめでたい事が積みかさなるように』という意味が重箱に込められているのです。
今では三段重ねが一般的ですが、
本来は四季を表すといわれている四段重ねが正式なのです。
1つ目の重には黒豆や田作り、カズノコなど祝いの肴を入れます。
2つ目の重には口取り、酢の物である伊達巻や紅白なますを入れます。
3つ目の重には、海や焼き物を入れ、おせち料理を楽しませてくれます。
それぞれの中に入れるものですが、時代も変わるとおせちも変化します。
現在では見た目の派手さ豪華さも手伝い焼き物が好まれるようになり、
二段は焼き物がメインで三段目は煮物になっています。
また、おせち料理には祝い肴の3種があります。
これはおせち料理の体裁が整う必需品といえるでしょう。
場所によって異なりますが、
関東では『黒豆・数の子・田作り』
関西では『黒豆・数の子、たたき牛蒡』
とあります。
おせち料理には、この3つの肴がなければ、
おせち料理として成り立たないくらい大切な存在になります。
黒豆は『マメに生きる』
数の子は『子孫繁栄』
田作りは『豊作や豊穣』
たたき牛蒡は『家の基礎』
としての由来や意味があります。
◆まとめ
スーパーやインターネットで気軽に購入できるようになったおせち料理。
昔と違って全部を手作りで済ませる家庭は少なくなっているでしょう。
しかし、おせち料理を食べるときに意味や由来を考えることはできます。
そうすることで新年への気持ちを新しくできるでしょう。