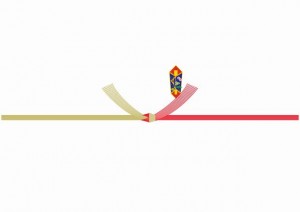忘年会というのは、会社などの組織ではなく仲間うちだけの会であれば、
気楽に楽しく過ごすということだけに神経を注げばいいので気が楽ですよね。
ところがサラリーマンなどのように組織の一員として働いている人にとっては、
単なる飲み会ということではありません。
大掛かりなことではないにしても、一年の締めくくりとなるような、
ある程度は形の整った会を意識してのこととなります。
そのような忘年会の初めの挨拶というのはどうすればいいのか?
目次
◆忘年会の初めの挨拶について
会社などの組織の忘年会において、
初めの挨拶として話すべき内容のおおまかな概要としては、
・長すぎず短かすぎず
・もらすことなく
・よどむことなく
・出しゃばることなく
などという事に注意して行うようにするというのが基本であります。
◆具体的にはどういうことなのか?
・長すぎず短かすぎずとは?
長すぎず短かすぎずというのは、
主催者は別の人であって、幹事はその会の進行役だという認識だからです。
忘年会の最初は、飛び込んできた人や仕事の延長を持ち込んでいる人もいて、
落ち着きがないものです。
そのまま忘年会になってしまうと、
せっかくの会がバラバラな感じになってしまいます。
参加者の気持ちが集中するように、
時間を少しかけてスタートを演出するということです。
つまりは開会宣言です。
そして、静かになって集中したら、後はシンプルに話すことがポイントです。
・もらすことなくとは?
もらすことなくというのは、
やむを得ないで参加できない人、遅れる人について、会に先立って紹介すること、
そして、寄付などがあったなら、その紹介も怠らないということです。
・よどむことなくとは?
よどむことなくというのは、
幹事はいわば事務局です。
ですから、聞き手に受けがよいようとか、
面白おかしく挨拶して拍手をもらおうとか、
そういった余計なことは考えないで、淡々と話せということです。
・出しゃばることなくとは?
出しゃばりことなくというのも同じですが、
盛り上げ役ですので、自らは一歩引いた立場であることを認識しましょう。
そして主催者やその会においてメインである人、
たとえば。。。送別会を兼ねているような場合での会社を離れる人。
などを、立ててというようなことです。
基本文としては、
皆さん、1年間ご苦労さまでした。
本日は1年の締めくくりとしましてゆっくりとくつろいで楽しく飲みましょう。
本日は御出席いただきありがとうございました。
加えて部長より、お祝いを頂戴いたしましたことを報告致します。
最初に●●部長より、お言葉を頂戴します。
◆最後に
一年の締めくくりである忘年会の幹事ともなれば、
結構重要な役割ということになります。
ですからある程度の演出が必要になります。
例えば。。。主催者挨拶の入れ方には特に注意が必要です。
一般的に忘年会の主催者は、その組織の長ということとなります。
そのため組織の長を立てて、
それでいて参加者が皆盛り上がる工夫も大事なことになります。
先ほどの寄付の話などは、
注目してもらうために先に話す方がいいこともあります。
それとは逆に、主催者の話の後に紹介する方が効果的ということもあります。
そういった組み立ても挨拶と同じく
・もらすことなく
・出しゃばることなく
サクッとできるとよいですよね。